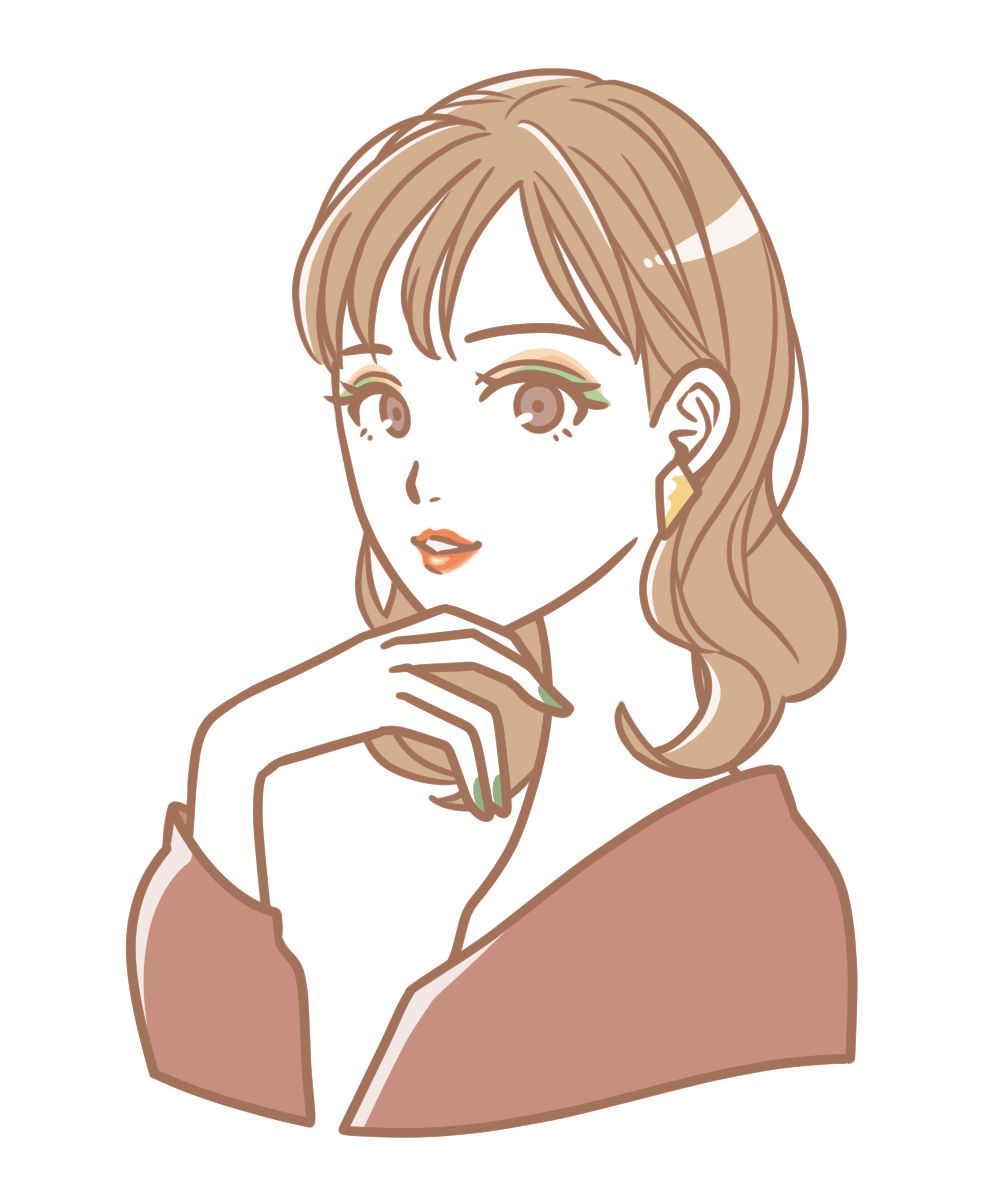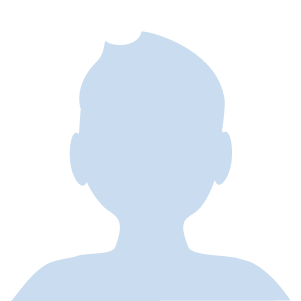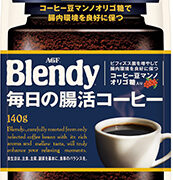子育てをしていると、悩みが尽きませんよね。
この記事にたどり着いたということは、普段からお子様のために尽力されている素敵な方だと思います。
毎日お疲れ様です!!
保育園で働いていると、
「子どもの好き嫌いが多い」・「栄養不足による子どもの成長が不安」
などのお悩みをよく耳にします。
私も一児の母なので、心配になる気持ちはよくわかります。
ですが、一言だけ言わせてください!
とは言っても気になるのが、今のお子様の成長ですよね。
そこで今回は、
好き嫌いの原因
好き嫌い克服法
について解説していきます。
ぜひ、参考にしていただけますと幸いです♪
好き嫌いの原因

赤ちゃんには、苦味や酸味を拒否する本能が備わっている。
味覚には、五味『苦味・酸味・甘味・塩味・旨味』がありますが、
苦味のある食品=「毒を含んでいる危険な食べ物」、
酸味のある食品=「腐敗している危険な食べ物」
ということを本能的に認識しているので、赤ちゃんは苦味と酸味に敏感です。
大人になると苦味や酸味が美味しいと感じるのは、様々な味の経験を積んだ結果、できあがる嗜好。
赤ちゃんが苦味と酸味を拒否するのは、当たり前な自然の摂理なのです。
味蕾細胞が多い(味に敏感)

人間には舌に味蕾という味を感じるセンサーがあります。
このセンサーは「甘み」「うまみ」「塩味」「酸味」「苦味」の5つを感じることができます。
味蕾は、
「赤ちゃん>大人>高齢者」
と、歳を追うごとに数は減少すると言われています。
- 昔は、ピーマンが苦くて食べられなかったのに、いつの間にか食べられるようになった。
- 梅干しが苦手だったのに、気付けば美味しいと思うようになっていた。
- 苦いだけだと思っていたコーヒーやビールが美味しく感じられるようになった。
これらは、「食経験を積んだ結果+味蕾が鈍感になっていっているから」
という訳なのです。
食経験が乏しい
子どもは、新しい食べ物を嫌う傾向にあります。
「食べたことのない味、食べたことのない料理」=「嫌い」
と判断してしまい、食わず嫌いになってしまうこともあります。
-
初めて新しい食べ物を与える時には、最新の注意を!!
初めての食材や料理を食べた際に不快を覚えると、
2度と食べたくなくなってしまう場合があります。反対に美味しいという感動や満足感を得ることができれば、
その食材や料理を好きになることが多いです。その為、ファーストコンタクトを大切にしましょう☆
過去に嫌な思いをしたことがある
作った料理に手をつけられずに、残されるのは悲しいもの・・・。
そして、子どもの成長も心配・・・。
そのような想いから、つい
「残さず食べなさい!」
「食べないと、鬼を呼ぶからね!」
などと、怖い顔で怖い声かけをしてしまってはいないでしょうか?
しかし、これは逆効果!
この状態が続くと、その食材(料理)を食べられるようになるどころか、
食事の時間自体も嫌いになってしまいます。
それは、もったいないことです。
大切なのは、子どもの気持ちに寄り添い、無理強いせず、
楽しいご飯の時間を演出することです。
好き嫌い克服法

まず、声を大にして言いたいことは
1.下処理を工夫する

- 魚の生臭さが苦手・・・
→新鮮な魚を選ぶ・生姜汁やカレー粉を使用する。 - 青物の青臭さが苦手・・・
→一度下茹でをしてから、調理に使用する。
苦手な匂いを取り除いたり、マスキングしてあげることで
食べられるようになる場合が多いです!
2.調理法を変える
- 鶏の照り焼きのぐにゃっと感が嫌・・・
→唐揚げや竜田揚げにして、パリッと仕上げる。 - 野菜のシャキシャキ感が嫌・・・
→長時間茹でる・フードプロセッサーにかけてペーストにする。
3.カットサイズを変える

- 千切りは、上手に食べることができないのが嫌・・・
→キッチンバサミや包丁で細かくカットしてあげる。 - 揚げ物が噛みきれなくて、嫌・・・
→1個の唐揚げを4等分にしたり、湯通しするのも一つの方法。
口腔機能が発達していない為に、上手に食べられないことが原因で、
その食材を食べたがらない場合があります。
3.味付けを変える
- カレー粉・粉チーズ・ソース・マヨネーズなどで味をマスキングする。
- ツナや挽肉など旨味のあるタンパク質と組み合わせる。
4.見た目を変える
- 野菜が目に見えないように、みじん切り、ペーストにする。
- 細切りにすることで、野菜の形状がわかりにくくなり、調味料の味が絡みやすくなる。
5.食器を変える

- 食材をすくいやすい形状の食器を選ぶ。
- アンパンマンやドラえもんなど、本人が喜ぶ絵柄の食器を取り入れる。
6.ご褒美シールを用意する
苦手なものを食べられた時は、盛大に褒めてあげましょう!
口から出したとしても、チャレンジしたこと(過程)も褒めてあげましょう!
7.子どもと一緒にクッキングをする
自主的に調理に関わることで、
「僕が作った!食べてみたい!」という心理が働き、
普段は食べない野菜も食べられる場合があります!
8.野菜を栽培する

自分で野菜を育てることで、その食材に対する興味・関心が高まります。
その結果、苦手野菜克服につながる可能性が非常に高いと言われています!
9.好き嫌いの原因を聞く
子どもがある程度、お話できるようになってきたら、
「どうして●●が嫌いなの?」と率直に聞いてみるのも一つの手!!
◇エピソード◇
以前、なんでもよく食べるのに、枝豆やグリーンピースを残す子がいました。
彼は、丸くて小さい見た目のものが苦手なようでした。
そこで私は、グリーンピースを潰し、枝豆はみじん切りにしました。
すると、 Aくんは、全て完食してくれたのです!!
10.食べ物に関する本を読む

カレーを作る前に、カレーの絵本を読んで、ご飯の期待感を高めることで、
苦手野菜にチャレンジしてみようという気力が湧く場合もありますよ。
11.集団の中で食べさせる
これは、保育園あるあるなのですが、
「家では、青物を全く食べない子が、保育園では、毎回完食する。」
という現象があります。
これは、「ママには甘えて良い」という気持ちと、
「保育園のお友達に刺激を受ける」という
両方が絡み合った結果であると考えられます!
12.お腹が空いた状態でご飯を食べるようにする
直前に間食をしないことが、ご飯を美味しく食べるポイントです!
13.家族揃って食事をとる

家族みんなで食事をすることは、子どもにとってメリットがあることが多くの研究によって示されています。
とは言ったものの、ライフスタイルの多様化により
家族全員が揃って食べることは難しいのが事実。
そんな時でも、
- 「水曜日の朝食は、家族揃って食べるようにする」
- 「日曜日の夕ご飯は家族一緒に食べるようにする」などと、ルールを決めてしまうのも一つの手ですよ♪
まとめ

好き嫌い克服に大切なことは、
「子どもに寄り添い、好き嫌いの原因を解明するよう努めること」。
子どもが苦手なものは、無理に食べさせることはせず、
ゆっくり長期戦で解決していきましょう!
「食事=楽しい時間」にすることが大切♡
お子様の好き嫌いが、改善していきますように・・・♪
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!